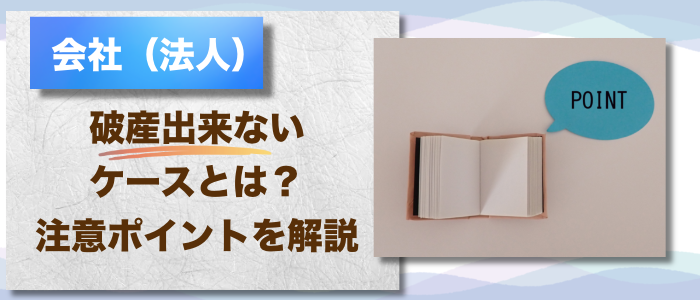
法人破産できるのは、支払不能や債務超過に陥っている状態であるのに加え、権利濫用にあたらず破産費用を納められる等の諸条件を満たした時だけです。
申立人の目線では当然満たすと考えられる要件ですが、倒産・廃業に踏み切る直前の判断が仇となり、思うように手続に入れない場合も考えられます。
本記事では、会社(法人)はいつでも・どんな状況でも破産させられるわけではないことをテーマに、下記について解説します。
目次
会社(法人)の破産を認めてもらうには「破産原因があること」及び「破産障害事由がないこと」を両方とも満たさなくてはなりません。
どちらか一方でも欠ければ、破産手続開始決定は発令されず、申立書を提出しても却下されてしまいます。
会社を破産させたくても出来ないケースを最初に整理しておくと、以下4つのパターンが挙げられます。
法人について破産手続開始決定が発令できるのは、法第15条もしくは第16条の原因がある時です。
詳しくはこの後解説しますが、今後の売上等で弁済の見込みがある程度立つ状態だと、たとえ収支ゼロでも手続開始にならない恐れがあります。
破産申立てにつき不当・不誠実な目的があると判断された場合、法第30条に基づき手続開始は認められません。
利害関係や経済規模の大きさ、弁済できなかった債務が法人格と共に消滅する手続である点を考慮すると、一部の例で権利濫用のリスクがあるからです。
法人の破産手続きでは、予納金と呼ばれる裁判手続の諸費用を支払う必要があります。
会社の状態によって金額の幅がありますが、最低でも20万円~50万円程度の予算となります。支払えない場合、破産手続は開始できません。
会社を倒産させる手続きには、民事再生・会社更生等の様々な種類があります。
これらに先に着手している場合、破産申立てを行っても却下される可能性があります。
通常、先に進めている手続きで処理した方が、債権回収額が大きくなると考えられるためです。
破産の申立ては形式さえ満たせば誰でも認められますが、いつでも出来るわけではありません。
返済資金の見込みが立つ限りは別の債務整理方法を選択すべきで、破産手続開始はあくまでも「本当にこれ以上返済できなくなったタイミング」に限定されるのです。
これを破産原因と言い、厳密には次のように定められています。
破産原因に該当するものとして、第1に支払不能が挙げられます。
第2条11項で次のように定められていますが、典型的には「滞納がある程度続き、回収予定の売上等の有無に関わらず到底支払えない」状況が挙げられます
支払いを停止すると、「支払不能」が推測されることになります。
会社の破産手続では、申立ての前に債権者へ内容証明郵便等を送って弁済停止を通知することで、支払不能の推測ありとします。
株式会社の破産手続では、第3に債務超過の状態が挙げられます。
法律では次のように定められています。貸借対照表ではなく、現実の資産を負債が上回っている状態です。
破産法では、債務超過を次のように定義しています。
合名会社・合資会社の場合は、債務超過を破産原因とすることが出来ず、破産原因は「支払不能」のみとされます。
債務がいくらに及ぼうと、存在する無限責任社員の個人資産及び収入で弁済しなくてはならないからです。
上記形態の会社が破産するなら、無限責任社員も同時に支払不能となっていること、つまり個人破産も開始することが前提となります。
決算書等では黒字企業であっても、支払不能や債務超過であると判断できる場合は、破産原因ありとして手続できます。
判断材料として、貸借対照表・損益計算書・残高試算表を直近分まで、その他にも収益予測を詳細に立てた書面が必要です。
支払不能の定義である「一般的かつ継続的に」弁済できない状況は、将来の売上がゼロもしくは弁済できない額であると裏付ける資料で疎明できます。
その他、与信がなく新規借入ができない状態(直近の銀行融資の謝絶歴)も、既に支払不能や債務超過の状態にあるとの判断の元になります。
会社の破産では、破産原因の有無等といった実体的な要件だけでなく、申立書や裁判管轄等の形式的な要件もチェックされます。
破産法で定められる形式的要件のうち、特に重要なのは「誰に申立権があるか」です。
有り得る破産できないパターンとして、経営者以外の株主その他の出資者が心配し、自分で申立書を提出するケースが挙げられます。
ごく基本的な部分ですが、下記3者だけが法人破産の申立権を有すると押さえましょう。
法人破産の申立権者として、第1に債務者であるその法人自身が挙げられます(破産法第18条第1項)。
債務者自ら申し立てることから「自己破産」と呼ばれ、一般化しています。
実際に破産申立てをする際は、取締役会・理事会で承認した時の議事録もしくは全員の同意書を申立書に添付します。
法人破産の申立権者として、第2に法人の取締役・理事・役員・清算人等が挙げられます(破産法第19条第1項2項)。
これらの個人は債務者に準ずるものとされ、手続は「準自己破産」と呼ばれます。
法人破産の申立権者として、第3に会社の債権者が挙げられます(破産法第18条第1項)。自己破産・準自己破産に対し、手続は「債権者破産」と呼ばれます。
債権者が法人を破産させる目的は、管財人による調査で財務状況の透明化を図り、財産隠しを防いでより多く回収することです。
つまり、経営についてよほど不信感を抱かせている場合と考えられます。
法人破産では、手続が滞ったり債権者を害したりすることのないよう、一定の事由があれば手続は開始できないとされます。
これを破産障害事由と言い、申立て前のセルフチェックで排除しておかなくてはなりません。
破産障害事由に関して注意したいのは、以下の3点です。
既に説明したように、破産法では「不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき」や「申立てが誠実にされたものでないとき」は手続を開始できないとされています。
申立て直前からの行動から、はじめから弁済する気がなかった、あるいは会社から資産を持ち出して守ろうとしたと判断される場合が該当します。
破産費用(予納金)の目安は、換価し配当すべき財産がある場合だと50万円~120万円程度とされます。
費用が捻出できない場合は、何らかの方法で申立て前に確保する他ありません。考えられる破産費用確保の手段として、次のようなものが挙げられます。
商品納入による売掛金債権等がある場合は、これを早めに回収することで一定の資金を作れます。
ただし、取引先に経営難を気取られて情報が広まらないよう注意しなければなりません。
加えて、回収した金額を返済に充てなかったことが破産障害事由に該当してしまう可能性にも気を付ける必要があります。
会社に不動産や営業車等がある場合は、これらを処分して資金を作る方法も考えられます。
この時も、査定をしっかり行い、適正な価格で買い取ってもらうよう注意しましょう。
低額で、ましてや代表者の親族や知己に買い取ってもらったりすると、後日、破産管財人から否認権を行使される恐れがあります。
代理弁護士の受任通知で支払を停止した後は、これまで返済に回っていた資金をストックして破産費用に充当できるでしょう。
やはり問題点として、早い段階で関係者に破産を気取られてしまう点が挙げられます。
状況によっては、受任通知を送付して蓄えをつくる余裕などなく、破産申立てに何とかすぐ着手しなければならない場合も十分考えられます。
会社の債務整理の方法には、法律に沿って行うものと私的に行うものの2種類があります。
破産手続は前者に分類され、同じ類型で民事再生・会社更生・特別清算の3つの手続きも存在します。
いずれかの手続を先に進めていた場合、基本的には破産手続が劣後するとされます。
破産手続と他の法的整理の方法が競合する場合は、先の手続が開始した時に破産手続開始の申立てが禁止されます。
申立てをしても破産障害事由に該当し、却下されてしまいます。
仮に破産申立てが先だったとしても、後に行った再生・更生・特別清算の手続きが優先され、破産は中断されます。
債権者との個別交渉・事業再生ADR制度等に沿う方法等の私的整理は、途中で要件を満たせば破産手続に移行できます。
ただ、債務の弁済が出来そうにない状態を債権者に知られている以上、会社及び経営陣のタイミングで移行できるとは限りません。
債権者に見切りをつけられ、早々に申立てされる可能性があります。
会社の破産では、ぎりぎりまで経営を続ける努力が裏目に出て、そのつもりがなかったにも関わらず手続開始の要件を満たせない場合が考えられます。
逆に、準備や検討が足りないまま破産手続が開始される可能性も捨てきれません。
法人破産したくても出来ない・然るべきタイミングに手続に移行できないといった失敗を防ぐため、基本的には次のことを心がけましょう。
経営難が見えた時に心がけたいのは、早めの弁護士への相談です。
借りては返す自転車操業に陥ったり、社員及び役員の生活を守ろうと個人資産の分離を図ったりした後だと、破産障害事由に該当するリスクが高まります。
経営者として悪意がないのは言うまでもないことですが、その証明手段や申立ての方法が複雑化し、手続きの遅延でかえって関係者に迷惑をかけることになりかねません。
弁護士に相談する前後のどちらであっても、会社の経営状況をなるべく漏らさないようにしましょう。
パニックになった債権者が押しかけてきて結果的に偏頗弁済(破産障害事由)になってしまったり、他に方法があったにも関わらず債権者破産の申立てが開始されたりしかねません。
会社破産の相談に対応する弁護士は、受任通知送付の要否を検討する等、会社にとって最善のやり方で情報をコントロールできます。
不安があれば、やはり早々に弁護士と今後の対応を打ち合わせするのが良いでしょう。
会社(法人)が破産できるのは、支払不能等の破産原因があり、不当・不誠実な申立て等の破産障害事由に該当しない場合に限られます。
破産を検討する状態なら通常満たせると考えられがちですが、そうとも限りません。
事業活動を通じて利害関係や収支の構造が複雑化している性質上、経営改善の努力が裏目に出て、申立て却下のリスクが生じることもあります。
会社破産や廃業が視野に入る時は、ひとまず客観的に経営状態を診断し、早めに最善の対応を見出すことが大切です。不安な時はすぐ弁護士に相談し、経営陣の判断だけで“延命”して破産手続を複雑化させないようにしましょう。